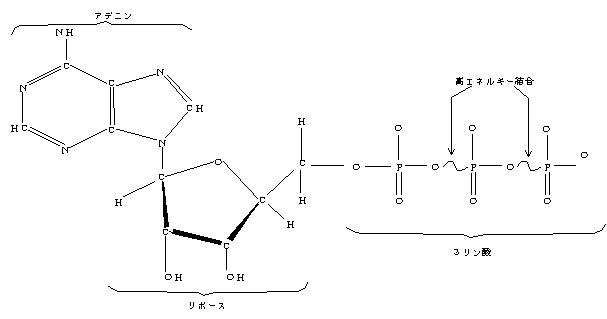 |
|
|
ATPとはAdnosine Tri-Phoshate(アデノシン3リン酸)の略であり、全ての生物においてエネルギー供給の道具として使われている分子である。光合成や呼吸といった活動によって得られたエネルギーは、いったんATPに蓄えられ、運搬されたATPから各個の細胞にエネルギーが移転されることによって、生物内部のエネルギー供給が成り立っている。
ヒトの成人男子は、平均して一日延べ190kgのATPを消耗する。人の体は常時50gほどのATPしか保持しておらず、このことから生物が何らかの形でATPを調達する必要があることがわかる。実際には、ATPは消耗された後、電気化学的反応によって再びATPに再生される。このATPの生成・消費のサイクル全体をひっくるめて、ATP回路という。
ATPの構造は、その名が示すとおり、アデニンと三つのリン酸から成り立っており、両者をリボースと呼ばれる糖の一種が繋いでいる(図1)。この中で、リン酸同士の結合は、リン酸とリボースもしくはリボースとアデニンとの結合に比べて遙かに高いエネルギーを持った結合(高エネルギー結合)である(図中、波線で示されている部分)。すなわち、この結合を切り離すときには高いエネルギーが放出される、ということである。このような特性が、エネルギー運搬に利用されているのである。
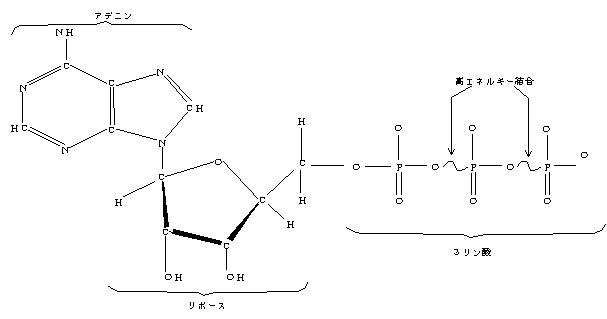 |
|
|
上述のように、ATPはエネルギーを放出してADP(AMP)とPiになる。ADP,Piは、 ATP合成系に輸送され、再びリン酸化によってエネルギーを与えられ、ATPとなる。リン酸化の過程には、基質準位のリン酸化と、化学浸透性リン酸化という二種類がある。基質準位のリン酸化は、非常に原始的な機構であり、ATP生産効率が低い。
化学浸透性リン酸化は、浸透圧のエネルギーを利用してリン酸化反応を進める機構である。浸透膜で仕切られた領域の一方に、H+を大量に移動させ(そのとき、もう一方の領域には同じ数のOH−が残ることになる)る。こうすることで、膜を挟んだ両側の間には、莫大な化学ポテンシャルエネルギーが生じる。このエネルギーをリン酸化反応のエネルギー源として、ATPを合成するのである。
H+を移動させる手段としては、酵素・補酵素による電子伝達系が用いられる。また、この電子伝達系を働かせるためのエネルギー源として、ミトコンドリアの酸化反応(動物、植物の暗反応),葉緑体の光還元反応(植物の明反応)が用いられる。電子伝達系に用いられる補酵素の主なものとして、NAD,NADP,FADがある。NAD,NADPにはニコチンアミド、FADにはリボフラビンという活性基が含まれている。ニコチンアミド,リボフラビンともにビタミンB誘導体であり、市販のドリンク剤によく含まれているものである。
ATP回路は、以上のようなシステムによって成り立っている。このようなシステムは、長い進化の過程の中で選択的に発達・採用されたものであると考えられ、現在の地球文明は未だこのような高度なエネルギー伝達系を人工的に作り出すに至っていない。クジラのひげやゼンマイなどという初歩的な技術とは比べものにならないといえるだろう。
参考文献:「現代生物学」上,W.ウォーレン,